こんにちは。弁護士法人アズバーズの弁護士 津城です。弁護士法人アズバーズでは,相続事件に力を入れて取り組んでおります。その一環として,相続についてのコラムを不定期で掲載いたします。今回は,2019年7月1日に施行された相続改正法のうち,創設された遺産分割前の預貯金の払い戻し制度ついて解説いたします。
1 創設された制度
改正により,遺産分割前の預貯金の払い戻し制度(民法第909条の2)が新たに創設されました。その条文は以下の通りです。
民法第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
要するに,遺産分割前であっても,一定の預貯金については,各共同相続人が引き出すことができることを定めています。
2 従来の取り扱い
この条文は,平成28年12月19日の最高裁判所大法廷決定(以下「平成28年決定」といいます。)を受けて定められたものです。
平成28年決定が示される以前は,預貯金債権が遺産に存在する場合,その債権は相続開始と同時に各共同相続人の相続分によって当然に分割され,各共同相続人が自分に帰属した債権については行使することが出来るものとなっておりました。
3 現在の取り扱いとその不都合
しかし,平成28年決定によって,預貯金債権も遺産分割の対象となることになりました。これにより,これまでは各共同相続人が遺産分割を待たずに行使できていた預貯金債権についても,遺産分割によってその帰属が確定しなければ,行使することが出来なくなりました。
しかし,平成28年決定による上記の取り扱いでは,不都合が生じます。被相続人に扶養されていた相続人は,被相続人が亡くなったとたんに預金を下ろせなくなり,その結果生活費に不自由をしたり,葬式の費用をねん出することも難しくなることもあるでしょう。
そのような事態を防ぐために,民法第909条の2は創設されました。
4 預貯金の払い戻し制度
民法第909条の2は,遺産の預貯金債権について,一定の金額については各共同相続人が遺産分割を待つことなく行使することができることとしました。
⑴ 払い戻し可能金額
払い戻し可能な金額は,預貯金債権の3分の1に,法定相続分を乗じた金額になります。例えば,預貯金債権が300万円,自己の相続分が2分の1であれば,50万円となります。
また,民法第909条の2においては,別の上限も設けられています。同一の金融機関に対して権利行使できる金額についても上限があるのです。
この上限金額は,法務省令で定められています。法務省令によると,上限は150万円となっています。預貯金債権の3分の1に法定相続分を乗じた金額が150万円を超えていたとしても,同一の金融機関に対して行使できる金額は150万円が上限になります。
⑵ 払い戻しを行った場合の遺産分割への影響
民法第909条の2によって預貯金の払い戻しを受けた場合には,遺産の一部の分割により,取得したとみなされることとなっています。そのため,相続財産の算定に当たっては,払い戻しを受けた預貯金債権についても加算されることになりますし,払い戻しを受けた共同相続人の取得分を計算するにあたっても,払い戻しを受けた金額を控除する必要があります。
5 さいごに
改正によって創出された民法第909条の2について紹介いたしました。弁護士法人アズバーズでは相続問題に力を入れております。相続問題でお困りの方はぜひ,ご相談くださいませ。
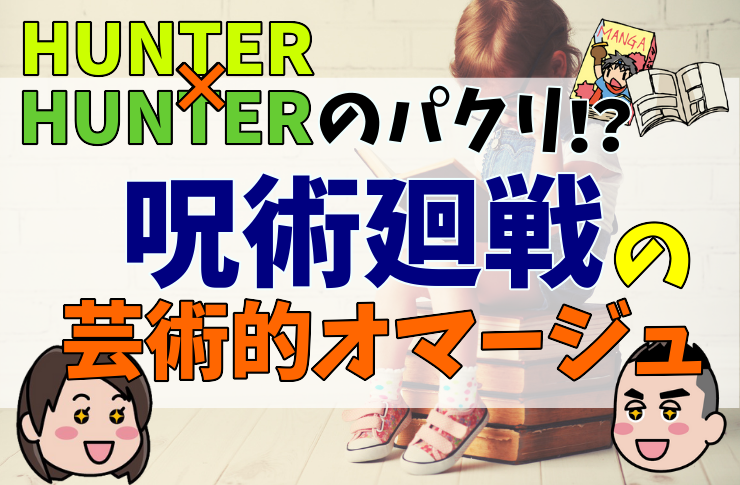
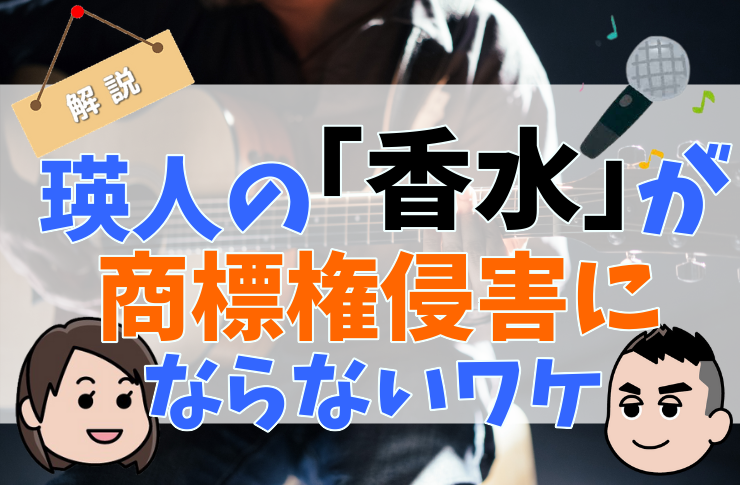
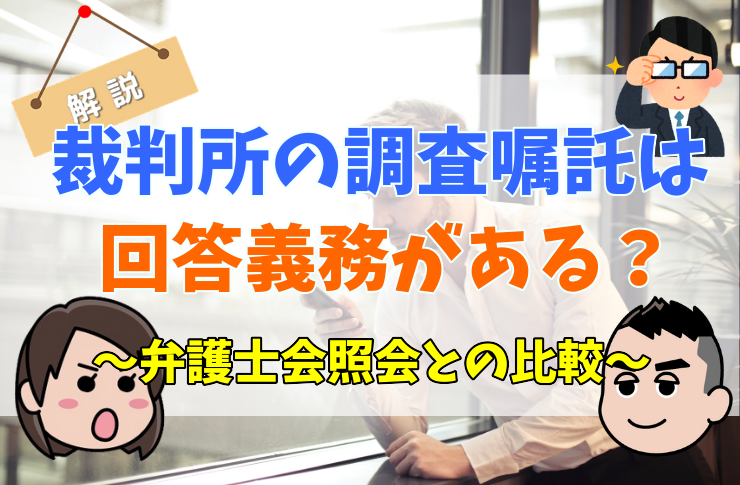



コメント